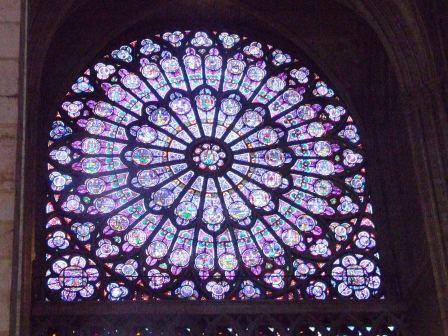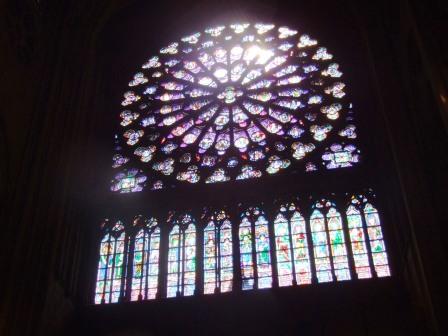|
���p���s�M��
�₪�āA��s�@�������Ԑ����Ƃ낤�Ƃ��邱��ɂȂ��āA�����葱�����ނ���������悤�@�����������ꂽ�B�@������ɕq���R�{�����������̎�𑖂点�n�߂����A�s�ӂɂ��̎肪�~�܂����B�u�g�N�������ҁh�͉p��łȂ�ƌ����̂��Ȃ��v�ƃu�c�u�c�B�܂�A�u�E�Ɓv�̗��Ɂg���E�h�Ƃ����I�������������܂�Ă��Ȃ��̂������B�������A�C�M���X���ĂƂ���́A��N�ސE�҂͗����Ⴂ���Ȃ����Ă��ƂȂ̂����H�����ŁA�R�{�̎肪�~�܂����̂́u�h���z�e���v�̍��ڂł������B7��8���ɔM�C�ōs�������O�~�[�e�B���O�̍ۂɐ������z�z���Ă��ꂽ���X�g�����Q���Ă����̂����A���߂Č��Ă݂�ƁA���̒��̉p���؍ݑ����ځi8��26���j�̗��Ɂu�\��ς݂����z�e�����̓p���̎���ɖY��Ă����v�Ƃ��������炾�B���������A�C�M���X�ł͔��܂�z�e���܂ŕ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ă̂��H
�e���̋��Ђ����Ǝ���
�������A��X�ɕ��C�M���X�s�M������菜���Ă��ꂽ�̂��A�����N�z�̂悤������i�ŗD�������{�l�X�`�����f�X�ł������B�u�E�Ɓv�ɂ��Ă��hretired�h�A �u�h���z�e���v�ɂ��Ắu�F�B���\��ς݁v�ł�낵���ł��傤�ƒ��J�ɋ����Ă��ꂽ���A�ʼn�X�̏��p�j�b�N�͂����܂����B����ƁA���x�̓C�M���X�̂�����Ă��闧�ꂪ��ÂɌ����Ă��āA�u�����A�������A�C�M���X�̓e�����x�����Ă��邩��g�h���z�e���h�܂Ń`�F�b�N���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�ƕ��������悤�ȋC���ɂȂ邱�Ƃ��ł��Ă����B�������A���������܂�����Ȃ��B�č��u�b�V��(Bush)�哝�̂̌��Ԃɏ���āA�u����(Blair)�O���C���N�ɏo�������肷�邩�炱��Ȃ��ƂɂȂ�̂��B�������A�A�����J�̃C���N�N�U�ɑ��Đ^����Ɏx���̈ӂ�\��������(Koizumi)�O�ƁA���łɖk���N�̋�(Kim)�����L��������BKBK�J���e�b�g�𑨂��āA�u�g�n���n�������h�Ƃ������t�́gBKBK�����h�ɗR������v�Ƃ��������܂ł������i���́Amade by myself)�قǂȂ̂�����B
�q�[�X���[�͒��X���[
�����������邤����BA�@�͂قƂ�Ǘ\�莞���ǂ����16:55�q�[�X���[�̊����H�ɒ����B9,000�L��12���ԋ߂��̒����Ȃ̂ɁA�قڃI���^�C���Ő��c����q�[�X���[�܂ʼn^�q���Ă����̂�����a�`�̃p�C���b�g�̘r�O�͑債�����̂��B���āA�X�y�C���A�|���g�K���A�I�����_�ȂǂƊC��Ŕe���������q�C�Z�p�����X�Ƃ��čq��Z�p�Ɏp����Ă���̂ł��낤���B�������A�a�`�̃X�`�����f�X�ƃp�C���b�g�̂��A�ŃC�M���X�̕]��������������ɍĂџT���������Ԃ��n�܂����B���̏�q�Ƃ��ǂ��Ȃ𗧂��ĒʘH�ɕ��ڂ��Ƃ��Ă��鎞�Ɂu��������s��̂Ȃ̂ŏ��X���҂����������v�Ƃ����A�i�E���X�����ꂽ�̂��B�������A���̌�A���������Ă��̃A�i�E���X���J��Ԃ���邾���ŁA�u���X�v�����X�ł͂Ȃ��Ȃ��āu�ő��v�ɂȂ��Ă����B��������`�o���ʼn�X��҂��ł���Ă���͂������炾�B
�s�����j�ށu�t�j�@�a�����������v
�r���ŋ@�������̓��e���u�o�X���Q��܂��̂ŏ��X�c�v�ɕς�����̂����A���̃o�X������Ɏp�������Ȃ��B�悤�₭�A�a�`�̃o�X����s�@�̑��O�Ɍ������̂́A�����ォ�ꂱ��1���ԉ߂������ł������B�������A�q�[�X���[�̒��X���[�Ԃ�́A����ɂƂǂ܂���̂ł͂Ȃ������B��X�̌������������R�����ɒ��ւ̗ł��Ă������炾�B��\���ɕ����ꂽ���ւ̐�ɏ\����̐R���䂪���ɕ���ł��āA���̔w��̕ǂɁuUK
Border�v�̓\�莆�������ɓ\���Ă���B�]���āA��X�͍s����́u�t�j(United Kingdom�F��p�鍑)��Border�i�����j�̕ǁv�ƑΛ�����`�ƂȂ�B�������A�R����̈ꕔ�ɂ��������������炸�唼�̐R���䂪�V��ł���̂ŁA�s��͒x�X�Ƃ��Đi�܂��A���lj�X���t�j�̌����ǂ���蔲����܂łɍX��1���Ԃ������Ă��܂����B��s�@�̏�q���͗\�ߕ������Ă���͂��Ȃ̂ɁA�����R���̐l�����\���z�u�����A�O���҂�҂����邾���҂����Ă����̂���p�鍑�̌ւ肾�Ƃł������̂��낤���B�t�j is not OK��!�o���őҋ@���Ă���͂��̐����ɘA������藧�Ă��Ȃ��܂ő������点�Ă�����X�́AUK Border�z������������ۂ�A��̂߂�悤�ȑ����ŋ�`�o���ɋ}�����B
���āA�q�[�X���[��`�o��
�����́A�����҂������т�Ă��邱�Ƃ��낤�B�悸�́A�a�`�y�ѓ����Ǘ��������ɐ�������Ă��l�т����Ȃ�����B�Ƃ��낪�A���l�т��悤�ɂ��A�����̎p���o�}���̐l�X�̗ւ̒��Ɍ����Ȃ��̂��B�҂������т�ċA������������̂��Ȃ��A�܂����B����Ƃ��A�A���̎�Ⴂ�A����[�A����Ȃ͂��͂Ȃ��B�r���~�߂Ďv�Ă��Ă���ƁA�����ɂ��Đ��`�h�̎R�{���u����ȂƂ���ɗ����~�܂��Ă�������f�ɂȂ�v�ƌ����ďo�}���̗ւ̊O�ɏo�悤�Ƃ������B����͒���ŁA�u�d�b�A�����Ȃ�����I�v�ƌ��O�d�b�̕����w�����B����Ȏ��ɂ͓�������Âɂ��Ă���̂���ԂȂ̂ɁB�Ă̒�A�r�f�I�J�������\������������X�̑O�Ɏp���������̂͐��\�b��̂��Ƃł������B�����āA�ɂ��₩�ɏ��Ȃ���u�h�b�L���J�����̐^�������Ă����������v�ƌy���ꌾ�B�a�`�@��q�̒x��ɂ��Ă͗\�ߐl�ÂĂɕ����Ă����炵���A�܂��A���������Ɏ��Ԃ�v����͓̂��풃�ю��Ȃ̂ŁA�قƂ�Ǐł炸�������Ă��ɑҋ@���Ă����̂��������B�����Ƃ��m�炸�A���p�j�b�N�Ɋׂ��Ă��܂�����X�̎p�͐����̃r�f�I�J�����̒��Ɏ��߂��邱�ƂƂȂ����킯�ł���B
|